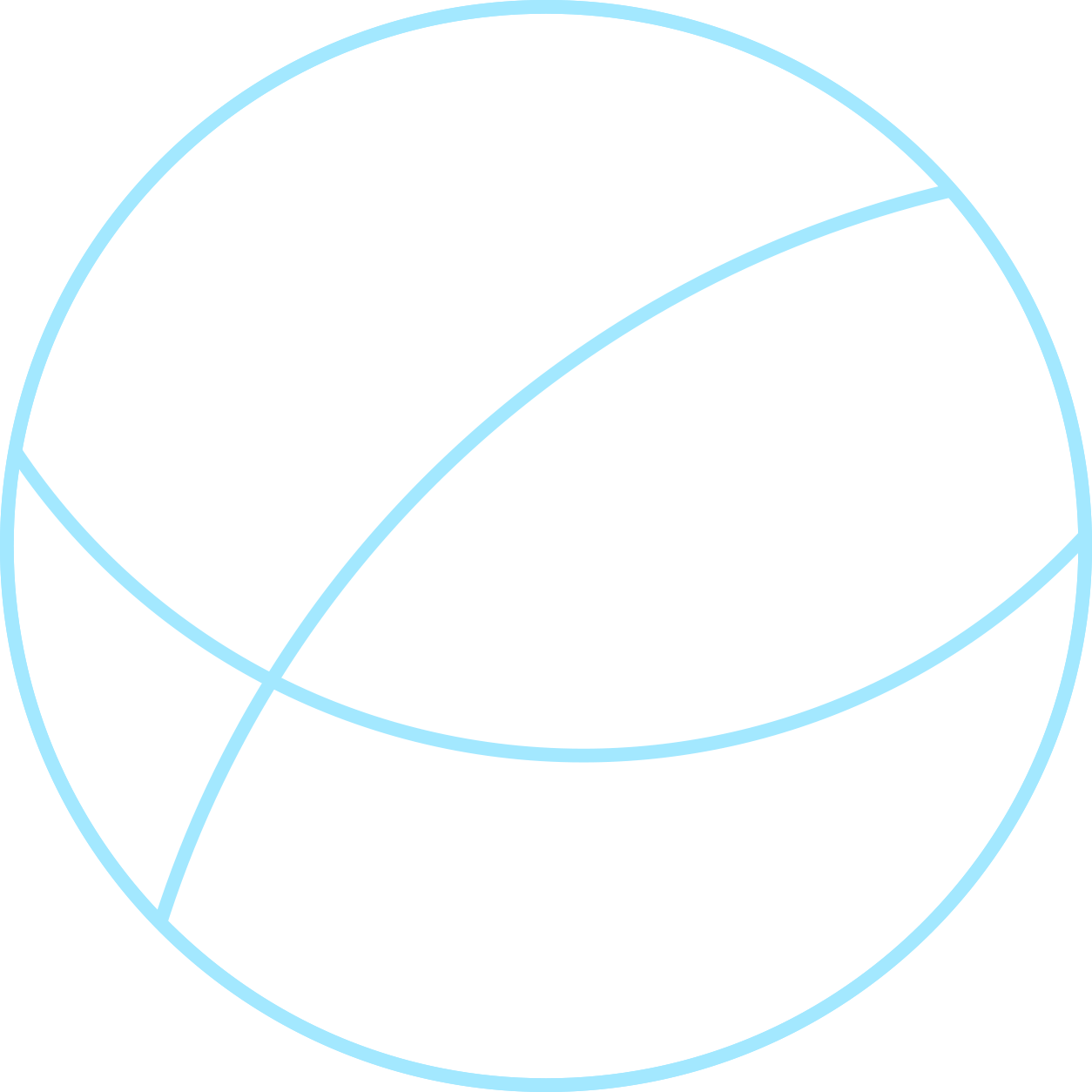オムニチュア社 第3回(前編) 顧客に愛されるデジタル製品を生み出す企業文化
Written byMarcus Otsuji

ライターからのメッセージ
第3回の「オムニチュア社の企業分析」は、製品をキーワードに前編・後編の2回に分けてお送りする。本前編では、ウェブ分析カテゴリを代表するオムニチュア製品SiteCatalystに焦点をあて、「成功を収める製品がどのように生み出されるのか」について学ぶべきポイントを掘り下げていく。後日配信の後編では「安定したビジネスとなるまでの開発の経過」についてお伝えしよう。
ピボットとは軸足を固定して、最善の方向を探索するべく、方向転換・路線変更を行うこと
はじめに
成功を収めているシリコンバレースタートアップ企業やDX戦略のすべてに共通しているのは、その中核に顧客に愛されるデジタル製品が存在していることだ。顧客の困難な問題を解決し、生活を便利かつ楽しいものにするデジタル製品やデジタル体験を生み出すことが、デジタル時代に勝利を掴む鍵となる。そこで、核心となるデジタル時代の競争力について疑問が出てくる。新旧含め成功している企業は、このような素晴らしいデジタル製品やデジタル体験をどのように開発しているのだろうか。
この質問に答えるには、UI/UXデザイン、最新の(アジャイル)ソフトウェア開発、DevOps、プロダクトマネジメントなど、運用及び管理についての多面的な視点や、クラウド、AI、ビッグ データ、API、サイバーセキュリティといった技術的な側面についての考慮が必要だが、日本企業がデジタル変革を取り入れる場合、経営幹部が直面する最大の課題はこれらではなく、むしろ文化的なもの(カルチャー)だろう。
それこそがまさに本稿でお伝えしたい点である。テクノロジーを採用し、これを活用するための管理機能を開発することが、デジタル変革の主な手順ではあるが、イノベーションのカルチャー、つまり、これまでにない新しい発想で製品を生み出す能力がなければ、この変革の成功は限られたものになってしまう。
例えば、シリコンバレーに目を向ける際、現地で使用・開発されている最新のテクノロジーについて理解する必要があるが、それ以上に重要なのは、革新的な製品を生み出す環境や状況を理解することである。オムニチュアの主力製品SiteCatalystを例にして見てみよう。
SiteCatalystについて
各分野をリードする製品は、そのすべてに明確な価値提案があり、競合企業と明確な差別化を図る必要がある。マーケティングの観点から見て、ウェブ利用の最大のメリットの1つは、その活動を数値化できることだが、それは決して容易ではない。当初は、ソフトウェアを使ってサーバーのログの解析を行っていたが、管理が難しく制限が多かった。
様々な「ウェブ解析」製品が市場に出回ったが、業界標準となったのは後発のSiteCatalystであった。SaaSという言葉ができるはるか前からSaaSによるサービスを提供し、直感的で洗練されたユーザーインターフェイスによって、シンプルかつ他に類を見ない操作性を生み出したことで、すぐに先見の明のあるデジタルマーケターたちから大きな支持を得た。では、競合製品がひしめく中、オムニチュアの創業者は、他社よりも優れた独自の機能や提供モデルのコンセプトをどのように思いついたのだろうか。
製品開発の経緯
オムニチュアの創業は2002年だが、共同創業者のジョン・ペスターナとジョシュ・ジェームズは、ブリガム・ヤング大学の学生だった1996年にオムニチュアの前身となる会社を立ち上げている。JP Graphics(すぐにJP Interactiveと改名)は、法人向けのウェブサイト制作企業として誕生した。 ドットコムブームが始まった時期でもあり、起業家を志すのは当然の選択だった。しかし、多くの人手が必要で拡大が難しい事業であり、かつ新たな競合他社が次々と参入するにつれて差別化も困難になってきた。このように魅力に乏しいビジネスモデルだった上に、ウェブサイトを制作し終わると、顧客は皆、まったく同じ質問をしてきた。「次は何をしたらいいんでしょう?」 と。
ピボット1
彼らは顧客にもっと価値のあるサービスを提供しようと、より拡張性の高いビジネスモデルを探し求め、自分たちが構築したウェブサイトの価値をさらに高める、さまざまなデジタルツールを開発した。そして立ち上げたサービスのうちの1つが軌道に乗り始めた。これはページビュー、訪問者数、その他のシンプルなウェブサイト指標を追跡するツールで、Superstatsと名付けられた。
ピボット2
Superstatsが成長するにつれ、彼らはその果てしない可能性に気がつき、このビジネス1本に専念するため、当初のウェブサイト制作を含むすべての業務を速やかに停止した。会社は「MyComputer.com」という名前で生まれ変わり、当時のその他オンラインサービスと同様に、無料広告サポートモデルを採用した。ウェブサイトのオーナーは、My Computer.comがウェブサイト上に広告を掲載することを条件に、無料でSuperstatsを利用できる仕組みだ。
Superstatsはすぐに200万のユーザーを集め、MyComputer.com を6000万ドルで買収するというオファーまで舞い込んできた。 すべてがハッピーエンドに向かっているように見えたが、その後、ドットコムブームはドットコムバブルへと変わり、6000万ドルの買収の話は頓挫して、オンライン広告事業に急ブレーキがかかった。当時のオンライン広告は、主に非常に業績の良いインターネットのスタートアップが使用するものであり、主流の広告業者はまだ参入していなかったのだ。
ピボット3
買収話は立ち消え、現金も使い果たし、広告市場から姿を消していく状況に陥ったジョンとジョシュは、大幅な人員削減という苦しい決断をすることになる。そして、事業継続に十分な顧客が移行することを期待して、無料広告サポートモデルから有料サブスクリプションモデルへと戦略を変更した。最終的に事業を継続できた2人だが、そこで立ち止まることはなかった。
ピボット4
市場観測や顧客とのやり取りから新たに学んだことを基に、大企業の顧客に完全に注力する好機だと考えた2人は、ただちにSMB事業を売却、会社名をオムニチュアへと変更した。その後は、これまでの連載記事でお伝えしたとおりである。オムニチュアとSiteCatalystはさらに進化を続け、エンタープライズ向けウェブ解析市場を完全に独占することとなった。
SiteCatalystは、天才発明家のアイデアでもなければ、市場調査やフォーカスグループの調査結果を反映したものでも、ウェブ解析のプロが出した構想でもない。物事が目まぐるしく動いていたインターネットの黎明期に、目の前の機会を逃さず、創業者が積極的かつ勇気を持って行った、数多くのピボットの結果にほかならない。
オムニチュア創業以前の出来事が1つでも欠けていたなら、間違いなくオムニチュアは失敗するか、凡庸な企業となっていただろう。同様に、それまで培った実際の経験や洞察無しにウェブ解析ツールを作っても、失敗に終わっていたに違いない。
SiteCatalyst開発の教訓は、製品の仕様や機能に関するものではない。それは、最適な組み合わせにたどり着くまで、創業者が次のビジネスモデルや次のテクノロジーへと柔軟に変化・適応した、そのプロセスや過程にある。まさにここに、技術的なものよりも重要な学びがあるのだ。
成功する製品の類似点
面白いことに初期のSiteCatalystには、今日の市場にある代表的な製品の多くと類似した点がある。これまでも数多く言及され、広く知られていることではあるが、今一度それぞれの特徴を説明しておこう。
Amazon Web Services
ここ10年で最も重要なエンタープライズ向けサービスがAmazon Web Services(AWS)であることに疑いの余地はない。AWSは会議室で誕生したのでもなければ、ジェフ・ベゾスのアイデアを採用したものでもない。Amazonのエンジニアが、膨れ上がっていく同社のウェブページの管理作業を楽にするために社内向けに開発したツールが基礎となっているのだ。
このツールがどんどん洗練されていき、ある時「これは他の開発者にも役立つかもしれない」と気がついた。この考えはまさに正しく、2021年の第1四半期にAWSの年間経常利益は5兆9,450億円と発表された。これは、Amazonの収益のほとんどを占める数字である。AWSは、Amazonの本業であるeコマース管理から意図せず生まれた技術的な派生製品であるが、今や本業をしのぐ収益を上げているのだ。
Slack
Salesforceに3兆082億円で買収されたSlackだが、元はTiny Speckという失敗に終わったゲームプラットフォーム企業であった。開発者同士のコミュニケーションを円滑にするために社内向けに開発されたツールを、CEOが企業向けのコミュニケーションプラットフォームとして幅広くアピールできると考え、この事業に対する投資家の承認を得ることに成功した。こうして、ゲーム関連の事業から完全にピボットし、新しいコミュニケーションツールに特化したSlackが誕生した。
Netflix
今でこそ世界最大の配信サービスとして知られているNetflixだが、元々はDVDのレンタル事業から始まった企業だ。ビジネスが巨大化して株式公開を行ったあと、CEOのリード・ヘイスティングスは、同社を有名にしたDVDレンタルのビジネスモデルを完全に取りやめるという非常に大胆な決断をする。当時、収益の100%が本事業によるものであったにも拘わらず、実績のないサブスクリプションベースの動画配信サービスに乗り換えたのだ。
そして、とても成功するとは思えないピボットを見事にやり遂げた後、サードパーティの動画をライセンス契約するだけでなく、Netflix独自の動画コンテンツを制作するというピボットに踏み切る。当初は嘲笑されていたものの、今ではオリジナルのテレビ番組や映画が賞を獲得し、数億人の視聴者に支えられ、世界で最も成功している動画配信サービスとなっている。2021年度、Netflixは1兆8,700億円もの莫大な金額をオリジナルコンテンツの制作につぎ込むと予想されている。
これらはオムニチュアのように市場を象徴するサービスであるが、その全てが、元々は現在知られている製品とは全く異なるものからスタートしたという点が興味深い。単なる偶然だという声もあるだろうが、こういったパターンの事例がシリコンバレーで頻発しており、その結果、重要な製品が生み出されているという事実はどう説明するのか。
広い目で見てみよう
一歩下がってシリコンバレーを俯瞰的に見ると理解しやすいかと思う。オムニチュアやSlackなど個々の企業の枠を超えて、同じような動きが起こっていないだろうか。
シリコンバレーには数多くの成功例がある。しかし、膨大な数のスタートアップ企業のうち、実績ある有能な創設者や経験豊富な出資者の支援があっても過半数が失敗するのが実情だ。しかし、それらの失敗例の原因をコミュニティに示すことで、これから誕生するベンチャー企業が成功する確率が高まる。
シリコンバレーは様々な意味での実験室となり、多くの仮説が発案され、実験が繰り返される。成功できるのは少数だが、失敗例の知識と経験が蓄積することで提供される学びはコミュニティ推進の原動力となっている。従って失敗は必然であり、イノベーションのプロセスに不可欠なものということになる。
オムニチュアの場合、創設者たちが新たなチャンス見極めることで、初期のビジネスモデルからうまくピボットができた。技術的なトレンドや景気循環、顧客の要望(暗黙の要求を含む)に柔軟に従い、ビジネスモデルや商品を全面的に変え、社名さえも数回変更した。そしてついにSiteCatalyst開発へとたどり着き、成功への扉を開いたのである。
大きな成功はオムニチュアのように同じ創設者によってもたらされる場合もあれば、全く新しい会社で起きる可能性もある。しかし一連のプロセスは同じである。関わった人々全員が将来を見据えながら積極的に関わり、失敗から学びながら必要に応じて勇気あるピボットを行い、チャンスが来たら素早く対応することが求められる。
結論
日本の企業がテクノロジーを採用して自社のデジタル製品を開発する場合はどうすればよいか。重要となるのは、イノベーションのプロセスは非常に混沌としていて予測不能であり、得てして失敗が成功を上回ることが多いことを理解することである。実際、これがデジタルイノベーションの特性なのだ。
ここで説明した原理を実行して成功した日本人を1人上げるなら、ソフトバンク社の孫正義氏になるだろう。孫氏は驚くくらい何度も失敗しているが、それらの失敗はつきもので、そこから学習し、前進し続けた結果、失敗が目立たなくなるほど数々の輝かしい成功を収めたのである。ある意味、孫氏の成功は、過去の失敗のおかげと言えるかもしれない。
これは知性や努力の問題ではなく、理解とカルチャーに関する問題なのだ。本稿で説明した原理に正しく沿ったカルチャーによって、新しいアイデアが生まれ、デジタル製品開発の成功とビジネスイノベーションが実現するのである。